各地域で孤独・孤立の対策や予防に取り組む関係機関の連携強化や、ネットワーク構築のきっかけづくりを目的に、地域連携ワークショップを県内3会場で開催しました。
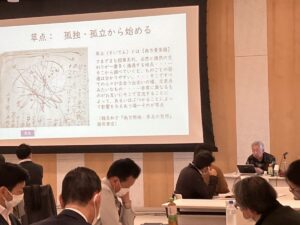
アドバイザーの津富さんからは、孤独・孤立にまつわる国内外の調査結果から、人との距離をとる方向に変化してきた人々の価値観や、不登校や相談相手のしない・できない子ども・若者の増加など、いま、起きている変調について解説いただきました。
特定の領域で対応するものではなく、よってたかって考えることが孤独・孤立を乗り越えるためのアプローチだと教えていただきました。

東近江三方よし基金は、個人や企業と社会的事業者を「ひたすらつなぐ」市民コミュニティ財団です。
“中間支援組織“と呼ばれる立場の山口さんはそう語ります。だから、活動団体が大事にしていることを見失わずに取り組み続けられるように伴走し、その取り組みを見える化して世に出すことで応援団を増やしていく。そうして、活動団体が孤立しないように「つながり」を増やしていく取り組みをご報告いただきました。

一般社団法人Team Norishiroは、「働く」を共通言語として生きづらさを抱える人と地域をつなぐ活動団体です。
障害者就業・生活支援センターに勤める野々村さんは、既存の制度の狭間にいる「充電中」の方々と出会います。
支援者の仕事は人の素敵なところを見つけることで、そのためには働く場が必要だと語ります。そこで目を付けたのが地域や企業の「困りごと」。当事者一人ひとりを「働きもん」と呼び、地域が困っているからあなたの力を貸してほしいと、扉を叩きます。支援の成果は、就労件数ではなく、いかに本人を応援する人が増えたか。互いにのりしろを少しずつ広げることで隙間をなくすために、地域を耕していく取り組みをご報告いただきました。
野々村さんの右手は一生懸命働きもんとつなぎ、その反対側の手は、山口さんががっちりつないでいる。そんな関係性がよく見える息ぴったりな2人の軽快なトークに強く惹きつけられました。
後半では、ご参加のみなさんと地域のアイテム探しを行いました。
「アイテム」とは、野々村さんのお話に登場するキーワードで、地域生活の中にある、ひと・もの・こと。野々村さんが見れば、「困りごと」も「働くこと」もアイテム。一人ひとりの、今この瞬間にちょうどいいアイテムを”使い倒す”といいます。そんな野々村さんの地域の見方をレクチャーいただき、見よう見まねで取り組んでみました。
「集会場」「お寺」「空き家」
「公園の掃除」「防災訓練」
「地域に長く住んでいる人」「時間がある人」「スナックのママ」
行政・社協・民間団体・企業など、視点の異なるさまざまなお立場の方が一緒にテーブルを囲むことで、地域に眠るたくさんのアイテムが見えてきました。

「孤独・孤立」という大きなテーマに集うことで、新しいつながりが生まれ、地域の見え方も変わってきます。今後も、そのような相互作用が生まれる場を企画してまいります。